伝耕は、「人」のオモテ・ウラ・ナカミを
よくよく攪拌(カクハン)した上で、ふたつの仕事をします。
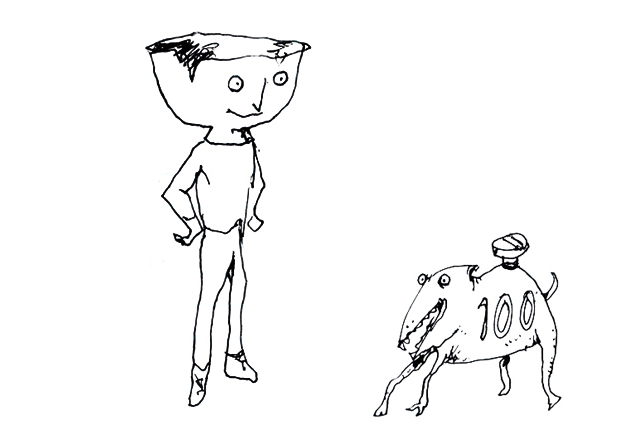
ひとつめ。 「人」が欲しいなと思うモノ・サービスを生み出し、それを市場でお客様に広めるための「マーケティングサポート」
ふたつめ。 生き抜く人と組織を作る「人財や組織開発のサポート」
そのために我々は、
- 顧客に価値を提供するために、マーケティングの現場で顧客の視点に立った実践を積む。
- 顧客に価値を提供し続ける人や組織をサポートするために、「人」に関する新しい知見を常に求め、顧客の視点をユニークな人財開発プログラムに生かし、現場で実践する。
伝耕のこれまでとこれから
~2016年から5年間を「賞味期限」とする仕事~
創業時の伝耕のミッションは
「人」の気持ちや考えをひきだし、ひもとき、組み立てることによって社会に貢献する。
でした。
■私たちの資源
伝耕は、ひとつめの分野-人が欲しいなと思うモノ・サービスを生み出し、それをお客様に広めるための「マーケティングサポート」-からスタートしました。
自らも「人」でありながら、対象としても「人」に尽きぬ興味があった我々は、自らも「人であるゆえに逃れられない主観のバリア(宇宙人なら客観的なはず?!)」と戦いながら、人をつぶさに観察し、人にありとあらゆることを問い、行動を共にし、人の認識・態度・行動を様々な手法で愚直に検証し続けました。その過程の中で「人」にまつわる、一見つじつまが合わない雑多な現象を数多く目の当たりにしてきました。私たちはそれを「不合理のパターン」と呼んでいます。
そういった「一見つじつまが合わない現象」、つまり「不合理のパターン」をクライアント様にご報告する際には、その説明の寄って立つ場所を、心理学・文化人類学・行動経済学・脳科学等の知見に求めました。その繰り返しの中で、私たちは、「不合理のパターン」の現象理解と分析を積み重ねてきたのです。
「合理的なつもりでも部分的に合理的でない存在が人である」というシンプルな記述は、2002年にプロスペクト理論がノーベル経済学賞を受賞したことにより、あまねく周知となる…はずでした。
しかし、それを論理が勝る(という前提の)ビジネスというある意味では「特殊な場」で、その事実を積極的に認め、それを基本的姿勢としてビジネスの構築に還元していくほど、ビジネスの「場」は「論理的ではない」。それもまた「人」の常の一つ。
私たち伝耕は、この前提に立ち、自分たちも含めた「不合理のパターン」理解に基づいた、「人」の織り成す様々な現象の理解を、ビジネス現場のマーケティング活動に生かしていただけるよう、営々とこの分野の仕事を続けております。
この分野における経験の蓄積と知見が伝耕の資産です。
さて、「不合理のパターン理解」、それは、言い換えるとつまり「予想通り不合理」を示す現象の理解。この現象をマーケティングの分野であぶり出し、理解し、マーケティング活動にお役に立つように加工するという仕事を続けるうちに、我々はとあることの重要性から目を離せなくなりました。
■私たちが直視した「ビジネス課題」
- ○ モノやサービスを売りたい・売り続けたい「人」や「組織」をサポートさせていただくには、「顧客」が直面している「予想通り不合理」を、マーケティングの中に組み込むだけでは、単発的な効果しか得られず、結局それは我らの自己満足に過ぎないのではないか?
- ○「顧客」が直面している不合理は、顧客に対峙する「人」や「組織」にもあてはまるという前提に立ち、この前提を「自分ごと」としてビジネスの「場」で活用できる「人」や「組織」を開発しなければ、持続的に価値を生み続けるという成果を得られないのではないか?
という課題認識です。
正直に申し上げますと、創業当時からこの根本的な課題について、認識「は」していました。
視野を広げてみれば、ビジネスの先頭を走る会社はすでにこの「課題」をうまく組み込んでいることに気づいたからです。しかしながら、伝耕のような小さな存在が取り組む領域としては「なんだか大変そうだから、手を出すのはやめておこう」と見て見ぬふりをしておりました。
そうこうするうち、数々の目覚ましい研究結果によって、「人」の「不合理のパターン」に関わる現象や新たな説明が次々と詳らかにされてきました。「人」は素晴らしい存在ではあるものの、同時に、その理想とする姿からは常に遠く、不合理で矛盾に満ち溢れている。よって、きわめて優秀な「人」でさえ、自我と信じている意識よりも、無意識に多く影響される存在であることの証左・証左…。
極端な話をします。
伝耕が提供するマーケティングサポートは最終的にモノやサービスが売れることに帰結します。よって、「人」の「不合理性・矛盾・無意識」に関する知見は、そのマーケティングの方法論に過ぎない、と片づけることもできます。
一方、「不合理性・矛盾・無意識」の部分を前提とした人財開発のプログラムは、最終的には「モノやサービスが売れること」に対して、実効性がありそうな半面、そのプロセスにおいては、「人」を困惑させる側面もあります。「皆さん、私も含め、人は愛すべき不合理な(かつ、矛盾だらけで、自分のことをよくわかっていない)存在なんですよ」という了解が必要となるからです。持続的かつ実効性がありそうな人財開発導入の前提とはいえ、これは下手をすれば、お金を払っていただく相手の面目をつぶしかねません。合理的な判断や決断を必要とされる(前提の)ビジネス場面で、「あなた(と、あなたの組織)もまた不合理!」、と小さな会社がそんなことを明言して果たして商売ができるのでしょうか?
しかしながら、それでも私たちは、「人」の不合理を「自分ごと」と理解し、ビジネスの「場」できる「人や組織」を開発することで、クライアント様をサポートすること、に踏み出す決心をしました。
この決心の遠景には、「人に関する研究成果」の進展があります。次々と明らかになるこれらの研究成果が示す内容に困惑し、目を背けること自体が「人と社会の持続」という大きな課題に対して本質的に「不合理」。むしろ、この困惑を突き抜けて、「不合理」とうまく伴走する決意さえしてしまえば、それは「人として生きる喜びの追求」につながるはず、という「未来からの視点」を意識したからです。
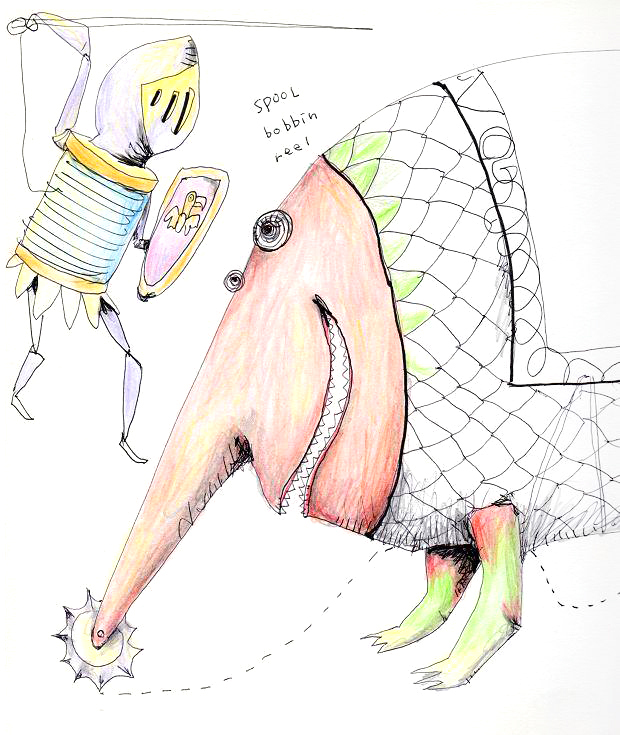
ここでいったん、人類の歴史を振り返ってみましょう。
我々は「農業革命」により恒常的な飢えから解放され、「産業革命」を経て生活の質が変わり、「情報革命」の恩恵で世界とつながりました。そして今、情報革命はさらに進み、「情報が生まれる主体」、つまり人の脳の探求により起きる革命、「脳革命(ニューロイノベーション)」なるものが進んでいます。農業革命が食べ物、産業革命が持ち物、ここまでは「人の外側の存在」が創造の対象でした。しかし情報革命以降は、その探求の方向は「人の内側にあるもの」に向けられています。現在進行する新たな革命の対象は、「不合理」やら「矛盾」やら「無意識的反応」を含む「人の中身としくみ」です。これにより、「人や社会そのもの」が大きく変わる可能性を秘めています。事実、ディープラーニングが進化を遂げ、「人間の仕事とは何か?」が既に問われています。次の世代を「利己的な自己の延長」として捉え、その行く末を考えるならば、我々は、「人」とは「予測通り不合理」な存在、と他人事のように評して、ちっぽけな面目云々を気にしているような場合ではありません。
歴史を俯瞰するマクロ視点では、「人」という存在は後戻りできない変化を求めてしまうようです。しかし一方で、「今・ここにある人」に焦点をあてるミクロ視点では、「人」は、昨日と続く変わらない今日の安心にすがりたい存在です。この欲望は本能的なものです。生きるための刻々かつ莫大な意思決定を最小化するために、限られた情報処理能力しか持たない我々「人」は、「今までと同じ続き」にある解を、ある一定量求めることで心の安らぎを得ます。逆に、過去との連続を全く意識できないことは、情報処理の負荷を増やします。それは、「不快」の素。つまり「変化」を声高に叫んでも、「不快」と感じれば、「人」は行動を起こそうとはしません。
「人」の行動は、「変化」という軸で観察すると、その変化軸の長さは「人」の情報処理能力の制限によって規定され、その行動は「変化の希求⇔変化の回避」活動の分散として観察される現象ではないでしょうか。
要するに「人とは変化軸の上をウロウロしている存在」と表現できるかもしれません。かつこの存在は、ちっぱけだけれど、なかなかに奇妙奇天烈かつ愉快な存在(客観的観察が可能な宇宙人なら、こんな風に評するかもしれません?!)であることでしょう。「人」の人生や会社の歴史でさえも「変化の希求⇔変化の回避」活動の連続体として捉えられる。ならば、マーケティング活動に対する「人」の反応も、人財・組織開発の取り組みや結果もこの軸の中に置くことができそうです。
■伝耕の新ミッション
創業時の伝耕のミッションは
「人」の気持ちや考えをひきだし、ひもとき、組み立てることによって社会に貢献する
であったことは冒頭に述べました。
今まで行ってきた“伝耕ならでは”の「人」の不合理を見据えたマーケティングサポートに加え、今回二つ目の柱として人材・組織開発のサポートを立てることにいたしました。
新たなフレーズを、伝耕のミッションに加えます。
新・伝耕ミッション:
「人」についての深い洞察に基づき、変化の回避と希求の間を揺れ動く「人」の気持ちや考えを、ひきだし、ひもとき、組み立てることによって社会に貢献する。
伝耕は、ささやかなスケールの会社です。
それゆえ幸いなことに、我々の変化のリスクは「極小」。
創業から「人」を見続けた伝耕。次の5年間は、マーケティングと人財開発のサポートという二本柱で、自らの存在をも学びほどきながら(Unlearn)、新たな人間らしさが実現する未来を求めて、楽しく思いっきりチャレンジをしてみようと思います。
Our services
Denko InsideOut
(マーケティング部門)
「あなたのビジネスを支える、伸ばす、変える」ことに不可欠な、商品・サービスの開発・マーケティングのお手伝いをします。具体的には、プロジェクトチームの創造性・生産性を刺激して全く新しいアイデアを生むためのファシリテーション、いささか込み入ったマーケティングのご相談を承ります。
マーケティング参謀
<マーケティングディレクション>
マーケティング古今伝授
<マーケティングトレーニング>
マーケティング探耕
<マーケティングリサーチ>
Denko UN’S (UnS)
(人財開発部門)
UNLIMITED, uncertain, unknown, unclear...確たるものに頼ることができないが、同時に限界をもつくらない。たくさんのUNで世の中にある確たるものを数多く否定することから始まる次の世代につながる拡がりを信じています。すでに世の中にある思考フレームをいったん解きほぐし(UNLEARN=学びほぐし)、不確実性をはじめとするたくさんのUNを味方につけて、生き抜く人財開発や組織開発のサポートを承ります。
「相互理解」をつくる
「キャリア」をつくる
「未来の組織」をつくる
「リーダー」をつくる
Our projects

6C・6D
伝耕の基本姿勢についてのちょっとカタイお話。未来視点の伝耕が大事にする姿勢・行動、それらを現出させるためにしつらえる「場」の設定方法について書いています。

Reframing the future
確かではない未来を作りながら、海外から発信する室橋さんのレポートです。
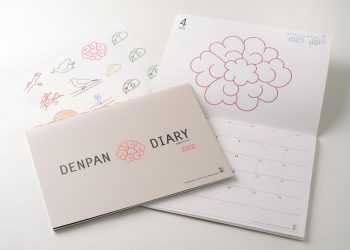
伝版ダイアリー
「コンセプトから人生を構築するスケジュール手帳」というありそうでなかったすぐれもの。伝耕が独自開発したコミュニケーションツール伝版を十二分に活用し、ビジョンを実現したいあなたのために毎年限定でお届けする手帳についてのご紹介です。

伝統産業への支援
日本の伝統産業の良さを国内外の視点を融合し、マーケティングの考え方・フレーム・方法を活用して強力にサポートします。
Who we are

西道広美
Hiromi Saido関西大学大学院 社会学研究科 博士 前期課程修了。(株)福武書店(現・ベネッセコーポレーション)を経て、P&Gにて市場分析・販売予測モデル構築、アジア・パシフィック地域の調査マネージメントを経験。その後、外部企業のブランド創出と再生、新製品開発に関わる調査マネージメントやワークショップのノウハウとツール開発に従事。

西野美徳
Minori Nishino東京大学文学部美術史学科卒業。P&GおよびMasterfoods Ltd.にて、化粧品とペットケアのマーケティングに従事。ブランドや商品戦略/企画・広告宣伝・CRMなどでマネージメントを経験。独立後は、日本最大手の化粧品会社・化学会社等に対して、マーケティング領域のコンサルティングや新規事業開発のサポート・コーチングを実施。

吉田純子
Junko Yoshida同志社大学大学院 文学研究科 社会学 専攻 修士課程修了。シンクタンクにて、主に消費財に関する深層インタビュー、ショッパー調査など、消費者密着型の調査プランニング・実施・分析に従事。消費者視点を活かした商品開発・ブランド創出のワークショップなどを担当。
What our clients say
伝耕さんは、戦うにあたって『戦場の地形』を正確に把握するのに物凄く重宝します。
消費者の頭の中の地形、狙う感情便益を立体的に洞察し、それを刺激するインサイトが何で、どういう意味合いでどう繋がっているのか。それらの消費者心理の関係性を把握することは、特に感情便益を売っている我々のような企業ではモノの比重が少ない分、何よりも決定的な情報です。質的調査に人材を欠く私の組織のような現場では、指示を出すことばかりに疲れた中で出会う、「リードしてくれてありがとう!」と思える助っ人でもあります。依頼する場合は目的さえ明確に投げ込めば、あとは全てをグイグイっと引っ張ってくれます。歯に衣着せない?遠慮無い?報告を聴き終わった頃には、意思決定にあたってのリスクとメリットのオッズが私の頭の中で明確になっていますね。

大手エンターテイメント企業
マーケティング部門長
単に調査がしたいだけなら、 もったいないかもしれません。
分かってないマネジメントに切り込みたいとき、チームメンバーだけでは仮説が偏っているなと感じたとき、何度も調査している間に一回りしてもとに戻ってきてしまったとき、どうせ調査しても分かりきったことしかでてこないだろうと半分あきらめているとき…。そんなときにお願いするのがいいかもしれません。アプローチはかなり直接的かつ独特のペースで展開されるため、お願いする方もどーんとかまえてください。もちろん期待は高く、どんなものを出してほしいかを熱く語れば、それ以上に役立つ結果を届けてくれるはずです。逆にテンション低いと、断られることもあるので気をつけてください。

大手フードチェーン 部長
もう一歩先に何かがあるような気がする…。そんな時に。
「マーケティング課題の解決に向けて一定の仮説はあるのだけれど、もう一歩先に何かがあるような気がする…」そんな時、いつも「ピンと来る」瞬間を提供してくれるのが伝耕さんです。テーマがチャレンジング且つエキサイティングであればあるほどに、一緒に組むのに最高のパートナーだと思います!

大手広告代理店 プランナー
その他、いろいろ。
- 組織の色々な人・場所に分散していた暗黙知を、ワークショップという場を設定することによって形式知に転換し、商品開発プロセスが迅速かつ効率的に変化した(外食産業)。
- 当初、プレーヤーとして優秀でも、組織が期待している役割を理解し、周りに働きかけ、巻き込んでいくことが不十分だったが、最近はチーム、センター全体を見渡した行動が見られるようになった。(キャリアデザイン研修参加企業)
